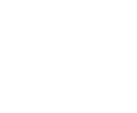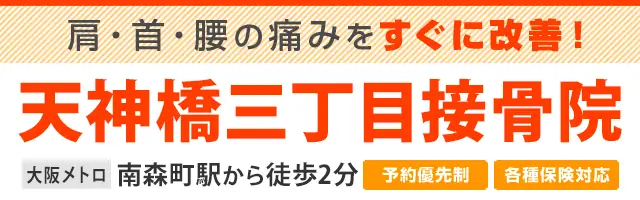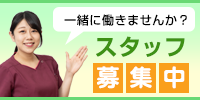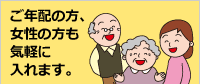巻き肩
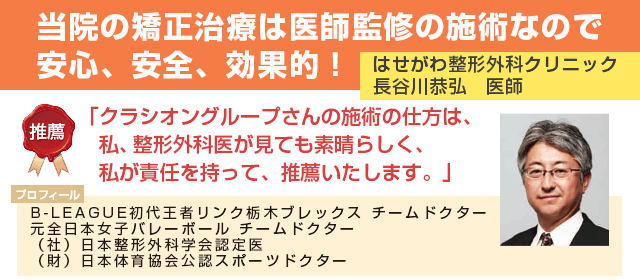

こんなお悩みはありませんか?

肩や首の痛み
巻き肩になることで、肩まわりや首に余分な負担がかかり、筋肉が緊張しやすくなります。その結果、慢性的な痛みやコリが生じることがあります。
背中の丸まり
姿勢が悪くなることで、背中が丸まった状態が続きます。その結果、背筋や胸筋のバランスが崩れ、さらに巻き肩が進行する原因となることがあります。
呼吸が浅くなる
肩が前に出ることで胸部が圧迫され、深い呼吸がしづらくなる場合があります。呼吸が浅くなることで酸素の供給が不十分になり、疲れやすさを感じることもあります。
体のバランスが崩れる
巻き肩の状態が続くと、全身のバランスに影響を及ぼす可能性があります。結果として、腰や膝など他の部位にまで負担がかかり、新たな不調につながることもあります。
見た目の印象
巻き肩は姿勢が悪く見えるため、見た目の印象に影響を及ぼすことがあります。特に女性の場合、外見に対する意識が高い方も多いため、気になるポイントのひとつとされています。
巻き肩について知っておくべきこと

1. 巻き肩の原因
巻き肩は、長時間にわたる不良姿勢(たとえば、デスクワークやスマートフォン使用時の前かがみの姿勢)によって引き起こされることが多くあります。特に、背中の筋肉が弱く、胸の筋肉が過度に緊張しているなど、筋力のアンバランスや日常的な動作の影響も要因のひとつです。
2. 巻き肩による影響
肩こりや首の痛み
肩まわりの筋肉が緊張しやすくなり、それによって首の筋肉にも負担がかかりやすくなります。
姿勢の悪化
背中が丸まり、胸が開きにくくなることで、姿勢の乱れが進行する可能性があります。
呼吸の浅さ
胸部が圧迫されることで深い呼吸がしづらくなり、酸素供給が不足しやすくなることがあります。
3. 巻き肩の予防と軽減方法
姿勢を意識する
正しい姿勢を意識することが大切です。肩を軽く後ろに引き、胸を開くように心がけましょう。
ストレッチを取り入れる
肩や胸の筋肉をストレッチして柔軟性を高めることが重要です。また、背中や肩甲骨まわりの筋肉をほぐすストレッチも効果が期待できます。
筋力トレーニングを行う
背中や肩の後ろ側(肩甲骨まわり)の筋肉を鍛えることで、姿勢を支える力が高まり、巻き肩の軽減が期待できます。特に、肩甲骨を内側に寄せるようなエクササイズが推奨されます。
作業環境の見直し
デスクワークを行う際は、パソコンのモニターを目線の高さに合わせたり、椅子の高さを調整するなど、良い姿勢を保ちやすい環境を整えることが重要です。
4. 意識的な休憩と動作の工夫
長時間同じ姿勢をとり続けることは避けましょう。定期的に立ち上がって体を動かしたり、肩を回すなどの軽い運動を取り入れることで、筋肉の緊張をやわらげることが期待されます。
症状の現れ方は?

1. 肩や首の痛み
肩こり
肩まわりの筋肉が前方へ引っ張られることで緊張しやすくなり、それが原因で肩こりや痛みが起きやすくなります。
首の不調
巻き肩の状態が続くと、首の筋肉にも負担がかかり、痛みやコリが生じることがあります。特に首が前に突き出た姿勢では、首まわりの筋肉が引き伸ばされ、不快感が増すことが考えられます。
2. 背中の丸まり(猫背)
姿勢の崩れ
巻き肩が進行すると、背中が丸くなりやすく、猫背のような姿勢が目立つことがあります。これにより、肩や背中への負担が増え、悪循環に陥る可能性があります。
肩甲骨の位置の変化
肩甲骨が外側に開き、肩のラインが前方に出ることで、肩の位置が不自然に見えることがあります。
3. 胸部の圧迫感や呼吸の浅さ
呼吸の浅さ
肩が前に出て胸が圧迫されることで、胸郭が広がりにくくなり、深い呼吸がしづらくなることがあります。呼吸が浅くなると、酸素の取り込み量が減少し、疲労感を感じやすくなることもあります。
胸の筋肉の緊張
巻き肩の状態が続くと、大胸筋や小胸筋といった胸部の筋肉が過度に緊張し、ストレスや圧迫感のような不快感につながることがあります。
4. 腕や手のしびれ
神経への圧迫の可能性
肩まわりの筋肉や筋膜の緊張が強くなると、腕や手に向かう神経が圧迫されることがあります。これにより、しびれやピリピリとした感覚が現れることもあります。
5. 肩の可動域の制限
動かしにくさ
肩が前方に巻き込まれることで、腕を上げる・後ろに回すといった動作がしにくくなることがあります。肩関節の可動域が狭まることで、日常動作に影響が出る可能性もあります。
6. 全身のバランスの崩れ
腰痛や膝への負担
姿勢の乱れによって身体全体のバランスが崩れ、結果として腰や膝に負担がかかり、痛みにつながることがあります。
歩行時の違和感
姿勢の崩れは歩き方にも影響を与えることがあり、体重のかかり方が偏ることで筋肉や関節に負担がかかる可能性があります。
その他の原因は?

1. 不良姿勢
デスクワークやスマートフォンの使用
長時間、前かがみの姿勢を続けることで、肩が自然と前に出て巻き肩が進みやすくなります。特にパソコンやスマートフォンを長時間使うと、肩甲骨周りの筋肉が弱まり、胸の筋肉が緊張することがあります。
猫背
背中が丸まると肩が前に出る状態が続き、巻き肩を引き起こす原因となります。
2. 筋力のアンバランス
背中の筋肉の弱さ
特に肩甲骨を引き寄せる筋肉(肩甲挙筋や僧帽筋など)が弱まると、肩が前に出やすくなります。
胸の筋肉の過緊張
大胸筋など胸の筋肉が過度に緊張している場合、肩が前に押し出され、巻き肩を助長することがあります。
3. 長時間の同じ姿勢
座りっぱなしや立ちっぱなし
長時間同じ姿勢を続けることは、肩や背中の筋肉に負担をかけ、姿勢を悪化させます。特にデスクワークで肩を前に突き出す姿勢が続くと、巻き肩になりやすくなります。
4. ストレスや緊張
精神的なストレス
ストレスがたまると、肩周りや首の筋肉が無意識に緊張し、巻き肩を引き起こすことがあります。精神的な疲れが身体に現れ、肩が前に出てしまうことがあるため注意が必要です。
5. 運動不足
筋力の低下
運動不足により肩甲骨周りの筋肉(特に背中の筋肉)が弱まると、肩が前に出やすくなります。また、胸の筋肉が過度に緊張し、巻き肩が進行しやすくなります。
6. 老化
加齢に伴う筋力低下
年齢を重ねると筋肉や靭帯の柔軟性が低下し、姿勢を支える力が弱くなります。これにより巻き肩が進行しやすくなることがあります。
7. 運動やスポーツの影響
不適切なトレーニング
ウェイトトレーニングなどで胸の筋肉ばかりを鍛え、背中の筋肉を鍛えない場合、筋力のバランスが崩れ、巻き肩を引き起こすことがあります。
巻き肩を放置するとどうなる?

1. 肩や首の慢性的な痛み・こり
肩こりや首の痛み
巻き肩になると肩甲骨周りの筋肉が常に緊張し、首や肩に負担がかかります。これが続くと、慢性的な肩こりや首の痛みを引き起こすことがあります。
筋肉の疲労蓄積
長期間にわたって筋肉が緊張し続けると疲れやすくなり、動かすたびに痛みを感じることもあります。
2. 姿勢の悪化
猫背や背中の丸まり
巻き肩を放置すると背中がさらに丸まり、猫背が悪化します。この姿勢の悪化が肩を前に押し出す悪循環を生みます。進行すると見た目にも不自然な姿勢が定着し、健康にも悪影響が出ます。
体のバランスの崩れ
姿勢の悪化により全身のバランスが崩れ、腰や膝に余計な負担がかかるようになります。
3. 呼吸の浅さ
胸部の圧迫
肩が前に丸まることで胸部が圧迫され、深い呼吸がしづらくなります。これにより酸素の供給が不足し、疲れやすくなったり集中力が低下したりすることがあります。
呼吸筋の衰弱
浅い呼吸が続くと呼吸を補助する筋肉が弱まり、さらなる身体の不調を引き起こす可能性があります。
4. 神経圧迫やしびれ
腕や手のしびれ
巻き肩が進行すると、肩周りの筋肉や神経が圧迫され、腕や手にしびれやチクチクした感覚が現れることがあります。放置すると神経障害が進行し、感覚異常が長期間続くこともあります。
5. 運動機能の低下
肩の可動域制限
肩が前に出ることで腕を上げたり後ろに回したりする動作が制限されます。動きが不自由になると、日常生活やスポーツに支障が出やすくなります。
筋力の低下
動かせる範囲が狭まることで肩周りの筋力も弱まり、さらなる動きの制限を招くことがあります。
6. 他の部位への影響
腰痛や膝痛
姿勢が崩れると体の重心がずれて、腰や膝に余計な負担がかかります。これが続くと痛みが慢性化することもあります。
全身のバランスの崩壊
姿勢不良は全身に影響を及ぼし、体全体のバランスを崩すことでさまざまな体調不良を引き起こす可能性があります。
7. 精神的・心理的な影響
ストレスの増加
身体の痛みや不快感が続くと精神的なストレスも増えます。また姿勢が悪いことで自信がなくなり、自己評価に悪影響を及ぼすことがあります。
当院の施術方法について

1. 姿勢の改善【TPC】
意識的に姿勢を正す
日常生活や仕事中に肩を後ろに引き、胸を開くことを意識しましょう。背筋を伸ばして姿勢が崩れないように心がけることが大切です。
座り方や立ち方の見直し
デスクワーク時は椅子の高さを調整し、モニターが目の高さになるように設定します。肩が前に突き出ないよう注意しましょう。立っている時は体重を左右均等にかけることを意識してください。
2. 筋力トレーニング
肩甲骨を寄せるエクササイズ
肩甲骨を引き寄せる筋肉を鍛えることが巻き肩改善の鍵です。ロウイングやリバースフライなどの運動が効果的です。
背中の筋肉を鍛える
僧帽筋や広背筋などの背中の筋肉を強化することで、肩の位置を安定させ巻き肩を改善できます。プルアップやダンベルを使ったトレーニングがおすすめです。
3. ストレッチ【上半身ストレッチ】
胸筋のストレッチ
巻き肩の原因となる胸筋の過緊張を緩和するため、胸筋(大胸筋)をストレッチします。壁に腕をかけて胸を開く、あるいは両手を後ろで組んで胸を広げる方法が効果的です。
肩甲骨周りのストレッチ
背中や肩甲骨周りの筋肉をほぐして肩の可動域を広げます。肩甲骨を動かすストレッチや肩回しを積極的に行いましょう。
4. マッサージや整体
肩や背中のマッサージ
筋肉の緊張を和らげるため、肩や背中のマッサージも有効です。特に巻き肩で緊張しやすい胸や肩周りをほぐすことで、痛みや不快感の軽減が期待できます。
軽減していく上でのポイント

巻き肩の予防と改善のための6つのポイント
1. 正しい姿勢を意識する
肩を後ろに引く
長時間座っている時や立っている時に、肩を後ろに引いて胸を開くことを意識しましょう。頭の位置も意識し、耳と肩が一直線になるように保ちます。
背筋を伸ばす
背中が丸まらないように背筋を伸ばすことを心掛けます。デスクワークやスマートフォン使用中も正しい姿勢を保つことが大切です。
モニターの位置を調整する
パソコンのモニターは目の高さに合わせ、肩が前に出ないようにしましょう。
2. 肩甲骨周りの筋力を強化する
肩甲骨を寄せるエクササイズ
リバースフライやロウイング、ダンベルを使った肩甲骨を引き寄せる運動を行いましょう。
背中の筋肉を鍛える
僧帽筋や広背筋など背中の筋肉を鍛えることで、肩の位置を安定させ巻き肩を防ぎます。プルアップやローイングが効果的です。
3. 胸筋の柔軟性を高める
胸筋のストレッチ
巻き肩の原因となる胸筋の過緊張を緩めるため、壁に腕をかけて胸を開くストレッチや、両手を後ろで組んで胸を広げるストレッチを行いましょう。
4. 肩周りのストレッチを行う
肩甲骨周りの柔軟性向上
肩回しや肩甲骨を引き寄せるストレッチで肩周りの柔軟性を高めましょう。
筋肉をほぐす
マッサージやフォームローラーを使って肩や背中の筋肉の緊張を和らげることも効果的です。
5. 定期的な休憩を取る
同じ姿勢を長時間続けない
デスクワークやスマホ使用時は30分に一度は立ち上がり、肩や背中を動かしましょう。
肩のストレッチや肩回しを習慣化
筋肉の緊張を和らげるため、定期的に肩を回したり上下に動かすことが大切です。
6. 運動や生活習慣の見直し
全身の筋力をバランスよく強化する
ウォーキング、ヨガ、ピラティスなど全身を使う運動で体全体のバランスを改善します。
運動習慣をつける
毎日の運動を習慣化して肩周りの筋力を強化し、巻き肩を予防しましょう。
監修

天神橋三丁目接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:鹿児島県志布志市
趣味・特技:ランニング、スポーツ観戦、ゲーム